会報「商工とやま」平成23年2・3月号
経営応援コーナー
〜ビジネスチャンスを活かすのはどれだけ効果的にアピールできるかで決まる!〜
第3回 心理効果をプレゼンテーションに活用する
前回は、「企画書」の内容をプレゼンテーションによって相手に伝えることの重要性、プレゼンテーションのコツについて解説しました。今回は、更に具体的にはどうすればよいのかを検討します。
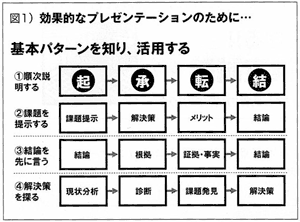 プレゼンテーションを行うにあたっては、次の4つの基本的なパターンがあります(図1)。
プレゼンテーションを行うにあたっては、次の4つの基本的なパターンがあります(図1)。
€順次説明型(帰納法)
課題提示型
¡結論先行型(演繹法)
¤解決策提示型
限られた時間の中で相手に伝えていくわけですから、どのパターンを使うことが効果的なのかを判断し、状況によって伝え方を変える必要があります。
例えば、結論先行型は演繹法とも言われ、物事を考える際、最初の前提から次の前提を導き、それを繰り返して、最後に必然的な結論を導く方法です。先に結論を述べてしまうので、プレゼンテーションを行う上でも、聞き手を惹きつけるには、一般的に演繹法が有効といわれています。この方法は業務報告などの場合でも有効です。
今度は、聞き手側の立場から考えてみたいと思います。
プレゼンテーションをする側としては、自分の意図を伝え、理解させ、共感してもらい、意思決定をさせて、企画の内容を一緒に進めてもらいたいわけですが、これを聞き手側としては、
€結果はどうなるの?
本当なのだろうか?
¡一体どのように進めるの?
¤事業の組み立ては?
と、最初は半信半疑で話を聞いています。それを、最終的には「もっと話を聞きたいな」という聞き手側の反応を得ることが重要です。
そういった意味で、話し手の意図と聞き手の興味を一致させることこそが効果的なプレゼンテーションを行う上で、大切なポイントになるのです。何度も繰り返しになりますが、プレゼンテーションの成功は、聞き手の心理を知らずして実現できないのです。
いくら優秀なプレゼンターでも、み○もんたクラスでない限り、プレゼンテーション時間を最大限活用することはとても困難です。
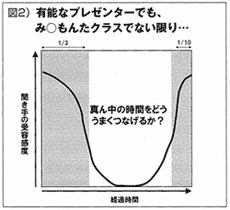 例えば、10分間のプレゼンテーション機会を与えられた場合でも、図2のように、最初の3分(約3分の1)は何とか聞き手を惹きつけることができますが、そこから少しずつ聞き手側の受容感度は下がって、中だるみの状態が発生します。その状態を作らないようにすることがプレゼンテーションを成功させる上で必要になってくるのです。
例えば、10分間のプレゼンテーション機会を与えられた場合でも、図2のように、最初の3分(約3分の1)は何とか聞き手を惹きつけることができますが、そこから少しずつ聞き手側の受容感度は下がって、中だるみの状態が発生します。その状態を作らないようにすることがプレゼンテーションを成功させる上で必要になってくるのです。
そのためには、専門的な用語の羅列になりますが、
・ハロー効果
・相手の意見の引用
・シンクロニー
・バンドワゴン効果
・イエス誘導話法
・ツァイガルニック効果(「続きはCMの後で…」等)
というような心理効果を用いてストーリーを味付けると、話す内容も、より聞き手に興味を抱かせる状態に作っていけるのです。
効果的なプレゼンテーションの手段は、「必ず相手の立場に立つ」。一般的にビジネスの世界で言われていることですが、プレゼンテーションを成功させるのも結論は同じということです。
次回、最終回は、本番でプレゼンテーションを成功させるための事前準備と、実践に向けたヒントをお伝えします。
当原稿の執筆は、中小企業応援センター事業の専門家/石橋孝史氏((株)ヒューマンサポート/取締役)にご協力をいただいております。
◎各種相談会、セミナー、事務組合をご利用ください!!
■お問い合わせ先 当所中小企業支援部 TEL:076-423-1171
◇シナリオを念入りにつくる基本パターンを活用していこう
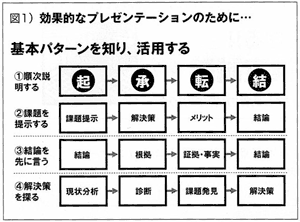 プレゼンテーションを行うにあたっては、次の4つの基本的なパターンがあります(図1)。
プレゼンテーションを行うにあたっては、次の4つの基本的なパターンがあります(図1)。€順次説明型(帰納法)
課題提示型
¡結論先行型(演繹法)
¤解決策提示型
限られた時間の中で相手に伝えていくわけですから、どのパターンを使うことが効果的なのかを判断し、状況によって伝え方を変える必要があります。
例えば、結論先行型は演繹法とも言われ、物事を考える際、最初の前提から次の前提を導き、それを繰り返して、最後に必然的な結論を導く方法です。先に結論を述べてしまうので、プレゼンテーションを行う上でも、聞き手を惹きつけるには、一般的に演繹法が有効といわれています。この方法は業務報告などの場合でも有効です。
◇プレゼンテーション成功のための実践 聞き手の心の状態から組み立てる
今度は、聞き手側の立場から考えてみたいと思います。
プレゼンテーションをする側としては、自分の意図を伝え、理解させ、共感してもらい、意思決定をさせて、企画の内容を一緒に進めてもらいたいわけですが、これを聞き手側としては、
€結果はどうなるの?
本当なのだろうか?
¡一体どのように進めるの?
¤事業の組み立ては?
と、最初は半信半疑で話を聞いています。それを、最終的には「もっと話を聞きたいな」という聞き手側の反応を得ることが重要です。
そういった意味で、話し手の意図と聞き手の興味を一致させることこそが効果的なプレゼンテーションを行う上で、大切なポイントになるのです。何度も繰り返しになりますが、プレゼンテーションの成功は、聞き手の心理を知らずして実現できないのです。
◇心理効果を使ってストーリーを味付ける
いくら優秀なプレゼンターでも、み○もんたクラスでない限り、プレゼンテーション時間を最大限活用することはとても困難です。
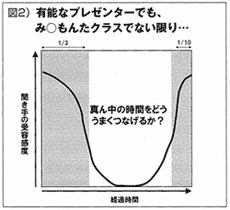 例えば、10分間のプレゼンテーション機会を与えられた場合でも、図2のように、最初の3分(約3分の1)は何とか聞き手を惹きつけることができますが、そこから少しずつ聞き手側の受容感度は下がって、中だるみの状態が発生します。その状態を作らないようにすることがプレゼンテーションを成功させる上で必要になってくるのです。
例えば、10分間のプレゼンテーション機会を与えられた場合でも、図2のように、最初の3分(約3分の1)は何とか聞き手を惹きつけることができますが、そこから少しずつ聞き手側の受容感度は下がって、中だるみの状態が発生します。その状態を作らないようにすることがプレゼンテーションを成功させる上で必要になってくるのです。そのためには、専門的な用語の羅列になりますが、
・ハロー効果
・相手の意見の引用
・シンクロニー
・バンドワゴン効果
・イエス誘導話法
・ツァイガルニック効果(「続きはCMの後で…」等)
というような心理効果を用いてストーリーを味付けると、話す内容も、より聞き手に興味を抱かせる状態に作っていけるのです。
効果的なプレゼンテーションの手段は、「必ず相手の立場に立つ」。一般的にビジネスの世界で言われていることですが、プレゼンテーションを成功させるのも結論は同じということです。
次回、最終回は、本番でプレゼンテーションを成功させるための事前準備と、実践に向けたヒントをお伝えします。
当原稿の執筆は、中小企業応援センター事業の専門家/石橋孝史氏((株)ヒューマンサポート/取締役)にご協力をいただいております。
◎各種相談会、セミナー、事務組合をご利用ください!!
■お問い合わせ先 当所中小企業支援部 TEL:076-423-1171